精神疾患で働けなくなってしまった方、日常生活でお困りの方へ
この記事の最終更新日 2025年3月5日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅
精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)に罹患してしまった方が心配することの一つとして、生活面、経済面に対する不安が挙げられます。
その際に利用できる制度をいくつかご紹介いたします。
罹患した時に避けていただきたいことは、症状などが安定していないにもかかわらず、無理して就労したりして状況を悪化させてしまうことです。
これらの制度を利用することで、休職、療養に専念し、精神疾患の症状と上手に付き合うことができ、社会復帰へと繋げていって欲しいと思っています。
※障害年金以外の制度については各相談窓口へお問い合わせいただければと思います。
障害年金
詳しくはこちら
傷病手当金(健康保険)
病気休業中に当人、その家族の生活を保障するために設けられた制度。病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるもの。
【相談窓口】
全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/)
各健康保険組合等
【1日額】
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のこと
【支給期間】
支給開始日から通算して1年6ヶ月
失業保険(失業保険)
雇用保険の被保険者が離職した場合でも、生活の心配をすることなく、就職活動を行い、早期の再就職をするために支給されるもの。
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)
要件の一つとして、「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」とあるため、精神疾患に罹患した場合の様に以下の状態に当てはまる場合は受給出来ない場合もあるのご注意ください。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
【相談窓口】
住所所轄職業安定所
【1日額】
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%
【支給期間】
離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間
生活保護
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づいて設立された制度。経済的に困窮してしまった日本国民は誰でも申請することができる。最後のセーフティーネット。
【相談窓口】
市区町村役場(福祉事務所)
【金額】
生活保護費は厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されるが、地域による生活水準の差などから、「基準額の地域差を設ける」とされています。
【期間】
期間は定められていない
※生活保護が廃止になる条件は収入が最低生活費を上回ること
【内容】
・生活扶助 ・住宅扶助 ・医療扶助 ・出産扶助
・教育扶助 ・生業扶助 ・介護扶助 ・葬祭扶助
※給付を受ける条件等の詳細は相談窓口にてご確認ください。
生活福祉資金貸付制度
厚生労働省の政策。精神疾患を含む障害者、低所得者、高齢者などの生活を経済的な側面から支え、かつ、在宅福祉と社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度。
※「貸付」なので、返済の義務あり
【相談窓口】
市区町村の社会福祉協議会
【貸付内容】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
【その他】
原則、連帯保証人を必要とするが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能。
(貸付金利子)
連帯保証人を立てる場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5%
自立支援医療制度
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。(医療費の上限を決めて、それ以上の医療費の負担がかからないよう代わりに公費で負担する制度)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html)
【相談窓口】
市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)
【対象】
・精神通院医療(精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等)・更生医療・育成医療
※治療費の上限は所得により異なり、市町村民税を年間235,000円以上納税している世帯に
属する精神疾患を持つ人は対象外
【給付内容】
月額総医療費 3割負担 → 1割負担(または高額療養費の自己負担限度額)
※月額総医療費の1割が上限額に満たない場合は1割)
【期間】
1年(継続利用の場合は更新申請が必要)
精神障害者保健福祉手帳
まず、「障害者手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称。
根拠となる法律等はそれぞれ異なるが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が受けられます。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
その中の一つである「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々に対して様々な支援策が受けられます。
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/tetyoukannren.html)
【相談窓口】
市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)
【対象】
等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであり、該当すると認定された人
【受けられる給付】
・各種税金の軽減
所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免など
・生活上の優遇措置
生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、NHKの受信料の免除、携帯電話料金の
割引など
その他福祉サービス等
・障害者福祉サービス事業者等
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、障害者支援施設(就労移行支援・就労継続支援・生活介護を行うものに限る)、 地域活動支援センター、小規模作業所など
・地域障害者就業センター
障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。
(https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/)
・障害者就業・生活支援センター
職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。
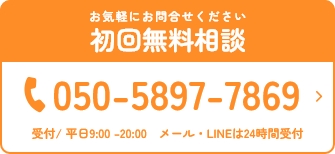
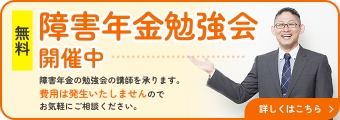


 初めての方へ
初めての方へ